| 神道霊学=古伝相承審神者神事道場(伯家神道)=神の気 ≫ |
伯家神道が審神神事(幽斎神事)であることを知る人は少ないようです。神人一体とは幽斎神事に入ることです。その神事を継承して現在に伝えたのが高濱清七郎です。そこで高濱清七郎は自ら創設した和学教授所の神事を「惟神道神伝相承審神古伝」「審神神事神伝相承修行法」と名称しました。現在伯家神道を名乗る人は多いですが審神者神事ができる人は稀です。唯一和学教授所の審神者神事の伝統を継承している玉鉾会では年に3回幽斎神事の大祭を行っております。伯家神道を皆様は祓いのみと考えておられますが、祓いを受け幽斎神事に入ることにより、そこに「神の気」なる「気」が生まれます。そこで祓いは幽斎神事の入り口であると言われています。祓われることにより、中国気功とは違う日本古来の「神の気」が存在するのです。その気を得てこそ神人一体の神の気が存在するお行が生まれるのです。そこで大方の間違いをしているのが自らで動かれるのです。又、そのように指導して人もいますが幽斎神事とは掛け離れたものです。神気を見出すまではひたすら待つのです。人間だれしもが持っている自らの気をよりよく高めるお行でもあるわけです。高濱清七郎の伝統を重んじ、今に伝える玉鉾会では50年間修業を積んで大成したものを「永川霊学」として神道講義と合わせて礼儀作法、祭式作法、幽斎神事、伯家神道行法を指導しています。幽斎神事なる神道霊学「永川霊学」を学ぶ唯一の道場が「玉鉾会」です。 |
|
 |
 |
 |
|
| 伯家神道行法練成会―「玉鉾会」の案内― ≫ |
*桑名道場開催日 午前10時~午後3時 *東京教室開催日 午前10時~午後4時 |
|||
| 桑名道場・東京教室 10,000円 | |||
|
和学教授所の伝統に倣って指導。
| ||
参加されたい人は下記のアドレスへご連絡下さい。 メールjgpdw440@yahoo.co.jp |
|||
楽古舎(玉鉾会)と伯家神道 玉鉾会の設立 その時のことを横井宮司は「日本の神とゴッド」をどのように話してよいのかと苦悩した事を度々私にお話しされました。 ⑤、近江神宮初代宮司は平田貫一です。鹿児島出身。昭和5年神宮皇學館館長(学長)。戦後、神社本庁事務総長(神社本庁総長)。新設皇学館大学初代学長。戦前に中村新子からの指導を受けておりますが一時的なものです。 玉鉾会の行法の特色(審神神事)
|
|||
| 玉鉾会-神道思想講座― ≫ |
伯家神道行法の他に神道思想を学び、和学の道を研鑽するのが高濱清七郎以来の和学教授所の和学の教えであり伝統です。内容は伯家神道行法に関わるご神名と神跡を学ぶための講座。(1回から12回) |
① 、午前、和学教授所と大和本学(中村新子と小笠原大和) ② 、午前、和学教授所の道統 ③ 、午前、伯家神道と審神者神事 ④ 、午前、神祇長(伯王)の流れと宮中祭祀 ⑤ 、午前、宮中八神殿と祝部殿(天皇の意義・御簾内の行) ⑥ 、午前、神祇官の衰退と白川伯王家 ⑦ 、午前、御巫と祝女 ⑧ 、午前、江戸時代の白川家(宮中祭祀の復活)徳川家と公家の関わり ⑨ 、午前、「八」の数霊 伯家神道と数霊 ⑩ 、午前、十種神寶と十種神寶行法 ⑪ 、午前、禊祓いの意義 ⑫ 、午前、高濱清七郎の謎 *「日 時」 毎月第一土曜日午前10時から午後4時まで。 但し変更がある場合もありますのでホームページで確認して下さい。 |
| 審神者神事大祭 令和7年2月23日 ≫ |
 |
高濱清七郎が提唱する審神者神伝相承和学教授所の流れを唯一現在に継承する「玉鉾会」では20数年ぶりに審神者神事を斎行。伯家神道を名乗っている会はいくつかありますが、正統に和学教授所の精神、神事伝統を継承しているのは「玉鉾会」のみです。20数年ぶりと言うのは、神事長である当主が初めて皆さんの前で審神者神事を斎行しました。午前10時から始まり午後1時終了。3時間の長丁場の神事です。皆さんは「お道の行」を伯家神道と言って勘違いしています。これはあくまで「お道の行」であって審神者神事に入るための祓いの修練の場です。神人一体となり、神が寄り付き神と共に遊ぶことより「神遊び」と言っております。神社で行われる神楽の原型です。 |
| 玉鉾会の年中行事 ≫ |
 白川家並びに和学教授所伝来の神事を斎行しているのが玉鉾会の年中行事です。 1月=「ひふみ粥神事」。イザナギ、イザナミ神の国生み神話に基づいて年始に行う神事。初めに湯立神事を行って参列者の湯浴みを行ってからお粥神事を行います。玉鉾会では40数年間行なっている古い神事です。その日に歳神様の恵方参りを行います。
|

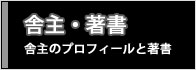








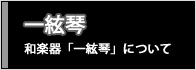
 白川伯王家に伝わる神道を称して、一般的に「伯家神道」「白川神道」という名称が浸透していますが、抑々は江戸時代おける諸家神道(吉田神道、橘家神道、賀茂神道など)その他の神道と区別するために使われている名称です。
白川伯王家に伝わる神道を称して、一般的に「伯家神道」「白川神道」という名称が浸透していますが、抑々は江戸時代おける諸家神道(吉田神道、橘家神道、賀茂神道など)その他の神道と区別するために使われている名称です。 玉鉾会の伯家神道は和学教授所の審神神事の伝統を唯一継承してきている会です。舎主が神行に入ったのは昭和53年です。当時は今のように興味を持つ人はなく、伯家神道の名称すら忘れられていました。
玉鉾会の伯家神道は和学教授所の審神神事の伝統を唯一継承してきている会です。舎主が神行に入ったのは昭和53年です。当時は今のように興味を持つ人はなく、伯家神道の名称すら忘れられていました。 ご神行の行法が「御生れ神事」(ミアレ)にあるという事です。「ミアレ」とは生まれ変わり、「ヨミガエル」というように健全な心身に再生されることにあります。「ミアレ」となるために「祓へ」があります。その為の禊祓いの行であると言えます。祓われることにより「ミタマ」が清められていく、そのお行を行っている訳です。
ご神行の行法が「御生れ神事」(ミアレ)にあるという事です。「ミアレ」とは生まれ変わり、「ヨミガエル」というように健全な心身に再生されることにあります。「ミアレ」となるために「祓へ」があります。その為の禊祓いの行であると言えます。祓われることにより「ミタマ」が清められていく、そのお行を行っている訳です。
